要介護認定でお金はいくらかかる?もらえるお金は?自己負担・支援制度まで解説!
「要介護になったら、一体いくらかかるの?」
「もらえるお金はあるの?」
親や自分の将来のことを考えると、ふと不安になるこの疑問。
介護は急に始まることが多く、費用の全体像が見えないままスタートしてしまいがちです。
要介護認定の申請自体は無料で行えます。
しかし、その後には「支給限度額を超えると全額自己負担」「おむつや住宅改修は原則自己負担」といった、知らなければ損をする費用のルールがいくつもあります。
本記事では、要介護認定にまつわるお金の仕組みをわかりやすく解説しつつ、負担を軽減できる支援制度や、介護費用を抑える工夫もあわせて紹介します。
高齢期の備えに早すぎることはありません。この記事を通じて、「もしものとき」に向けた準備の第一歩を踏み出してみませんか。

取締役/理学療法士上村 理絵
日本から寝たきり(寝かせきり)を無くすことを使命とする
家族がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう日常生活に必要な身体機能のリハビリに特化したディサービスを運営しています。
ご覧いただきました弊社のホームページにご案内した通り、寝たきり率が世界で最も高い日本ではリハビリを受けられない難民とも言うべき高齢者が年々増加し喫緊の社会保障制度の課題だと考えております。
そこで、この社会問題に一緒に取り組んでくれる志のあるリハトレーナーの募集を行っております。利用者・ご家族があきらめていた事を可能に変える為に…。 ぜひ、あなたからのご応募をお待ちしています!
1.要介護認定にかかるお金は?
まずは、要介護認定にかかるお金について解説します。
1-1.申請自体にかかるお金は無料
要介護認定の申請は、市区町村の窓口で無料で行えます。この手続きは、本人だけでなく家族やケアマネージャー、地域包括支援センターの職員などが代理で行うことも可能です。
申請の流れは以下のとおりです。
- 【申請】市区町村の介護保険窓口で申請書を提出
- 【訪問調査】調査員が自宅を訪問し、心身の状態を確認
- 【主治医意見書】主治医が心身の状態や診断内容を記載
- 【認定審査会】専門家が調査結果と意見書をもとに審査
- 【結果通知】認定結果が郵送で届く
このうち、申請から認定・通知までは基本的にすべて無料で受けられます。
ただし、「主治医意見書」の作成にかかる診察料については有料となるため、注意が必要です。
1-2.介護サービスは支給限度額を超えると全額自己負担
要介護認定を受けると、介護保険を利用して自己負担1割から3割でさまざまな介護サービスを受けられます。
しかし、要介護度ごとに決められた「支給限度額」を超えた場合は、全額自己負担となります。
要介護度と支給限度額の関係は次のとおりです。
| 要介護度 | 支給限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
例えば、要介護2の方の支給限度額は月額19万7,050円です。
この限度額を超えてサービスを利用した場合、その超過分には介護保険が適用されず、利用者が全額を支払う必要があります。
ただし、限度額は地域区分によって若干の前後がある点には注意が必要です。地域区分については「要介護認定でサービス利用するお金の仕組み(デイサービスの場合)」で詳しく解説します。
また、同じ限度額内でも、訪問・通所・施設系などの複数サービスを併用することで上限に達しやすくなるため、ケアマネージャーと相談しながら計画的に利用することが大切です。
1-3.おむつや住宅改装は基本的に自己負担
要介護状態になると必要となるおむつや住宅のバリアフリー改修なども、基本的には全額自己負担です。
介護保険を利用できるのは一般的には介護サービスの利用のみであるため、介護に関わる全ての費用に保険が適用できるわけではありません。
ただし、自治体によっては介護に必要なおむつ代や住宅改装費の助成を受けられる制度もあります。
活用には条件や手続きがあるため、ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談するのが安心です。
なお、具体的にかかる金額やお金が足りないときの対処法などは、以下の記事でも解説しています。
関連記事:親の介護費用はいくらかかる?負担の実態と費用を抑えるポイント
2.要介護認定でサービス利用するお金の仕組み(デイサービスの場合)
ここからは要介護認定でサービスを利用する際にかかるお金の仕組みを、デイサービスを例に解説します。ただし、一般的にはケアマネージャーや地域包括支援センターなどが費用を算定してくれるため、複雑な仕組みを利用者側が覚えておく必要はありません。
2-1.要介護度+利用サービス+施設規模+利用時間で基本単位が決定
介護サービスの費用は、以下の3つの要素によって基本単位が決まります。
- 要介護度(要支援1〜要介護5)
- 利用するサービスの種類(訪問介護、通所リハビリなど)
- 利用する施設の規模(デイサービスの場合)
- 1回あたりや1月あたりの利用時間や頻度
下記の表では、次の条件における利用時間と単位の関係を記載しているので参考にしてください。
| 要介護度 | 要介護1 |
| 利用するサービス | 通所介護(デイサービス) |
| 利用する施設の規模 | 通常規模型 ※前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750名以下のデイサービス |
| 利用時間 | 単位数 |
|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 370単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 388単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 570単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 584単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 658単位 |
| 8時間以上9時間未満 | 669単位 |
基本単位は制度上の計算のベースとなるもので、その後に加算や地域調整、自己負担割合などが加味されて最終的な金額が決まります。
そのため、この時点では「大まかな費用感を決める基準」として捉えるとよいでしょう。
なお、単位は1単位10円が基本となり、地域によって加算される仕組みです。
2-2.サービス提供体制強化加算を追加
介護保険サービスでは、基本単位に加えて「サービス提供体制強化加算」と呼ばれる追加の単位が加わることで、費用が変動します。サービス提供体制強化加算とは通常のサービス利用とは別に次のようなサービスを追加で依頼する場合に適用されるものです。
| 加算の種類 | 内容 |
|---|---|
| 生活機能向上連携加算 | 生活機能を向上させるためのリハビリを提供。 |
| 個別機能訓練加算 | 利用者ごとに個別に計画を作成して機能訓練を実施 |
| ADL維持等加算 | 日常生活動作(ADL)の維持・改善状況が一定を超えた場合に加算。 |
| 入浴介助加算 | 入浴介助を行った場合に1回につき加算。 |
加算の内容や適用条件はサービス事業所によって異なるため、「どの加算がどれくらい費用に影響するか」は、ケアマネージャーや事業所と相談して確認することが大切です。
2-3.地域区分がかけられる
介護サービスにかかる費用は住んでいる地域によって地域区分が加算され、地域区分と利用するサービスによって1単位の単価が変わります。地域区分が導入されている理由は、介護職員の賃金や物価の違いを反映させるためです。
地域区分は8段階に分かれており、最も高い1級地でデイサービスを利用する場合は1単位=10.9円として介護費用が計算されます。(デイサービスの場合)
地域区分と単位の関係は下表を参考にしてください。
| 地域区分 | 単位 | 地域例 |
|---|---|---|
| 1級地 | 10.90円 | 東京23区 |
| 2級地 | 10.72円 | 横浜市、川崎市、町田市、大阪市など |
| 3級地 | 10.68円 | さいたま市、千葉市、八王子市、名古屋市など |
| 4級地 | 10.54円 | 牛久市、船橋市、相模原市など |
| 5級地 | 10.45円 | 水戸市、市川市、横須賀市など |
| 6級地 | 10.27円 | 仙台市、川越市、明石市など |
| 7級地 | 10.14円 | 札幌市、栃木市、木更津市、北九州市など |
| その他 | 10円 | その他地域 |
地域加算は利用者が選べるものではなく、サービスを提供する事業所が所在する地域に応じて自動的に適用されます。
デイサービスや施設を選ぶ際には、費用の違いに影響する要素として確認しておくとよいでしょう。
2-4.収入に合わせた自己負担割合をかけて金額を決定
介護サービスの費用は基本単位や地域加算などで決まった金額に対して、利用者の収入に応じた自己負担割合をかけて算出します。
年金暮らしなどの高齢者の場合は基本的に1割負担が設定されていますが、以下の所得の場合は2割~3割負担の場合もあります。
| 年間所得 | 負担割合 |
|---|---|
| 280~340万円未満 | 2割 |
| 340万円以上 | 3割 |
例えば、あるサービスの単位数が10,000単位、地域単価が10円、自己負担割合が1割の場合、利用者の支払額は10,000単位 × 10円 × 10% = 1万円となります。自己負担割合が3割なら3倍の3万円です。
この仕組みによって、収入に応じた公平な負担が実現されています。
3.要介護でかかるお金の平均は?
要介護でかかるお金の平均は2024年(令和6年)に行われた生命保険に関する全国実態調査によると、月額約8万9,500円となっています。
この数字には、訪問介護やデイサービスなどの介護サービス費用に加え、福祉用具のレンタル費用や医療費、さらに介護に伴う交通費や日用品費も含まれています。
また、厚生労働省の介護保険サービスの料金目安ページでは、要介護度に応じた介護サービス費用の例も示されています。
例えば、要介護5の方が多床室(相部屋)の特別養護老人ホームを利用した場合にかかる費用の目安は次のとおりです。
| 施設サービス費(1割負担) | 約26,130円(871単位×30日=26,130) |
| 居住費 | 約27,450円(915円/日) |
| 食費 | 約43,350円(1,445円/日) |
| 日常生活費 | 約10,000円(施設により設定されます。) |
| 合計 | 約106,930円 |
これらの数字を踏まえると、介護費用はサービスの内容や利用状況、地域差、医療費の有無によって変動しますが、平均的には月に8万円から10万円程度の費用がかかると考えておくとよいでしょう。
介護費用を抑えるためには、要介護度を高めないよう機能維持・改善に努めることや、公的な補助や支援制度を上手に活用することが重要です。
なお、介護費用をはじめ、介護に関する不安が強い場合は、介護全体の知識を少しずつ高めていくことも欠かせません。
弊社リタポンテは「寝たきりを日本からなくす」ことを目標にするリハビリ専門のデイサービスです。
介護費用をかけないためには、まずは介護について正しい理解を持ち、寝たきりを防ぐための行動を取ることが大切です。
無料のLINEお友達登録では、寝たきりを防ぐための予防方法や日本の介護制度などについて、包み隠さずお話しています。
寝たきりを防ぎ、自分や家族にかかる介護費用を最小限にするためにも、下記よりお友達登録して、まずは正しい情報を手に入れましょう。
4.要介護認定でもらえるお金はある?
要介護認定を受けたことでもらえるお金はありません。しかし、介護を理由とした休業や住宅修繕など、公的な支援を受けること自体は可能です。
ここでは介護費用を抑えるために利用できる給付金などの支援を紹介します。
4-1.介護休業給付金
要介護の家族を介護するために仕事を休む場合、一定の条件を満たせば「介護休業給付金」という公的給付金を受け取れます。
介護休業給付金は雇用保険に加入している労働者が対象で、対象家族1人につき、最大で93日間(最大3回)までの介護休業期間に対し、休業前賃金の67%が給付されます。
利用するための主な条件は以下のとおりです。
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上※1 にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること。)を必要とする状態にある家族※2を、介護するための休業であること。
※1 ここでいう「2週間以上」とは、対象介護休業の期間ではなく、対象家族が常時介護を必要とする期間です。
※2 被保険者の、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の状況の者を含む。)、父母(養父母を含む。)、子(養子を含む。)、配偶者の父母、被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫 - 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
この制度では、介護が必要な家族を抱える働く人が経済的な負担を軽減し、安心して介護に専念できるよう支援しています。申請手続きや詳しい条件については、勤務先の人事担当や最寄りのハローワークに相談するとよいでしょう。
4-2.居宅介護住宅改修費
居宅介護住宅改修費は、要介護者が自宅で安全に生活できるよう、住宅の改修費用を補助する制度です。介護保険の給付対象となり、必要な手すりの設置や段差の解消、滑り止めの施工など、生活環境を整える工事に対して支援が受けられます。
改修費用のうち20万円を上限に、原則として7割から9割が介護保険から給付されます。具体的な改修工事の対象は以下を参考にしてください。
- 廊下や階段に手すりを取り付ける
- 段差の解消(スロープの設置など)
- 滑りにくい床材への変更
- 扉の交換や引き戸への変更
- 洋式便器への取り換え
- 上記の改修に付随する下地補強など
申請は市区町村の介護保険窓口を通じて行い、ケアマネージャーが必要性の判断や工事内容の調整をサポートします。なお、同一の住宅に対して改修費用の給付は複数回に分けて利用できる場合もあります。
また、補助はあくまで本人の要介護認定に基づくものであり、夫が利用した後でも妻が別の改修内容で利用することができ、引っ越した先でも新たに申請可能です。
住宅の安全性を高め、介護負担の軽減につなげる重要な支援制度なので、ぜひ活用を検討しましょう。
4-3.家族介護慰労金
要介護4や要介護5などの重度要介護者を1年以上、介護サービスを利用せずに在宅介護している場合、家族介護慰労金を利用できる可能性があります。
家族介護慰労金は要介護者の家族が介護を長期間続けることによる負担や苦労を軽減するため、一部の自治体が支給している支援金です。
例えば、大阪市では以下の条件を満たす方に対して、年額10万円の家族介護慰労金を給付しています。
【大阪市】家族介護慰労金の条件
次の1から5までの要件をすべて満たしている方
- 要介護者および介護者が1年以上継続して大阪市内に居住している(住所を有する)こと。
- 介護者は、要介護者と同居または同一敷地内もしくは隣地に居住して介護を行っている家族、または要介護者と1年以上同居し、現に要介護者の介護を行っている方であること。
- 要介護者が、介護保険の要介護認定を受け、1年以上要介護4または5に該当すること。
- 要介護者が、要介護4または5に該当する期間に、すべての介護保険サービスを1年以上継続して利用していないこと。(1年間で7日間以内の短期入所(ショートステイ)の利用は差し支えありません。) ただし、医療機関に入院した場合は、入院期間を除いて1年以上であること。
- 介護保険サービスを利用していない期間に、要介護者および介護者の世帯が市民税非課税であること。
注 介護者が複数いる場合でも、申請できるのは他の介護者の同意を得た代表者1人です。
引用:家族介護慰労金|大阪市
ただし、家族介護慰労金は国の介護保険制度の一環ではなく、自治体ごとに設置の有無や支給条件、金額が異なります。そのため、お住まいの市区町村の役所や介護保険窓口で詳細を確認することが必要です。
また、近年では介護サービスを利用するケースが一般的であるため、家族介護慰労金を廃止する自治体も増えています。
4-4.高額介護サービス費
高額介護サービス費は1か月あたりの介護サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が支給され、負担が軽減される制度です。
高額介護サービス費が利用できる利用者負担の上限額は所得によって、以下のように区分が分けられています。
| 区分 | 負担の上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
| 市町村民課税~課税所得380万円(年収770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税かつ前年の公的年金等種入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯)15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
この制度を利用するには、市区町村の窓口に申請する必要があり、給付は原則として後払い方式です。給付が認められれば、過払い分が払い戻される形で経済的な負担を抑えられます。
申請方法や詳細は、居住する自治体の介護保険窓口に相談してください。
4-5.高額医療・高額介護合算養育費
医療費と介護サービスの自己負担がどちらも高額になる場合に、経済的負担を軽減するための制度が「高額医療・高額介護合算療養費」です。
高額医療・高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の自己負担額が基準額を上回った場合、申請することで給付を受けられる給付金です。
医療保険上の世帯単位で合算されるため、高齢夫婦を含む世帯で暮している場合は該当する可能性も高くなります。
具体的な基準額は、年齢と年収によって以下のように変わります。
| 75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 | |
| 介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+被用者保険または国民健康保険 | ||
| 年収約1,160万円~ | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
| 年収約770~約1,160万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
| 年収約370~約770万円 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
| ~年収約370万円 | 56万円 | 56万円 | 60万円 |
| 市町村民税世代非課税等 | 31万円 | 31万円 | 34万 |
| 市町村民税世代非課税等(年金収入80万円以下等) | 19万(注) | 19万(注) | |
引用:高額介護合算療養費制度 概要|内閣府
自己負担の限度額は所得や世帯状況によって異なりますが、合算によって負担が大きくなることを防ぎ、安心して医療と介護のサービスを受けられます。
申請は居住する市区町村の窓口で行い、医療保険と介護保険の双方の領収書や支払い証明書が必要です。
詳しい手続きや条件については、市区町村の介護保険担当窓口や医療保険の窓口に相談してください。
4-6.医療費控除
介護保険サービスのうち、保健師や看護師等により行われる療養上の世話または診療の補助等が行われるものについては医療費控除の対象となります。
所得税の軽減を受けられるので、介護費用の削減に効果的です。他にも居宅サービスなどにおいて使用されるおむつの料金については、医師から「おむつ使用証明書」が発行されている場合は、医療費控除の対象です。
上手に活用すれば所得税を大幅に削減できるため、医療費の領収書を保存して確定申告を行いましょう。
利用している介護保険サービスのうち何が医療費控除の対象となるかは、ケアマネージャーなどに相談することをおすすめします。
また、国税庁が展開している「税についての相談窓口」を活用するのも良いでしょう。
4-7.障害者控除
障害者控除は、本人や扶養家族が障害者である場合に適用される所得控除の制度です。例えば、認知症などを患っている要介護者を介護している場合に利用が可能です。
具体的な控除額は区分によって次のように分けられています。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
引用:障害者控除の金額|国税庁
なお、特別障がい者とは障害がい者の中でも、以下のような重度の障がいのある方を指します。
- 身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が一級又は二級と記載されている方
- 療育手帳に障がいの程度が重度として「A」(「マルA」、「A2」など)と表示されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
- 重度の知的障がい者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
引用:特別障害者|国在庁
同居する家族などが障がい者認定を受けた場合は利用しましょう。
4-8.おむつの支給や購入の助成
自治体によってはおむつの支給や購入に関して助成を行っているケースもあります。例えば、さいたま市では条件を満たしている場合に、ひと月上限6,000円の利用券が支給されます。
他にも杉並区では障害者おむつ一覧から月額9,000円以内のおむつを選ぶことが可能です。申請を出すことで申請月の翌月に自宅におむつが届きます。
ただし、対象者の条件や助成の範囲が自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の福祉課や介護保険窓口で確認が必要です。
このような助成制度を活用することで、介護にかかる経済的負担を軽減し、必要なおむつを安心して利用できます。
4-9.福祉用具購入費制度
自治体によっては福祉用具の購入費用を助成しているケースもあります。介護保険の給付対象となり、車椅子や介護用ベッド、歩行器などの購入に対して、一定の費用が支給されます。
具体的には年間で10万円を上限に、1割から3割の自己負担で対象となる福祉用具の購入が可能です。
購入可能な福祉用具には、以下のようなものがあります。
- 車椅子
- 介護用ベッド
- 特殊寝台付属品(手すりなど)
- 歩行器・杖
- 排泄関連用品(ポータブルトイレなど)
申請は市区町村の介護保険窓口で行い、ケアマネージャーの助言を受けながら必要な福祉用具を選定します。購入後は領収書や支払い証明書を提出して給付申請を行う流れです。
福祉用具購入費制度を活用することで、高額になりがちな介護用具の購入費用の負担を軽減し、より質の高い介護環境を整えられます。
5.補助金以外で介護のお金を抑える方法は?
介護のお金を抑えるためには、補助金の利用以外に自分で対策を行うことも重要です。ここでは介護費用を抑えるために、自分でできる対策を解説します。
5-1.デイサービス利用の場合は半日型も併用する
半日型のデイサービスは、通常よりも提供時間が短いため、費用も比較的安くなります。
また、レクリエーションを中心としたものだけでなく、リハビリに特化したサービスもあり、身体機能の維持・向上を目的とした支援が受けられます。
リハビリ専門のデイサービスでは、理学療法士などの専門職と連携し、短時間でも効果的なリハビリを受けることが可能です。
半日型介護サービスの具体的なメリットは以下のとおりです。
- 利用時間が短いため自己負担額が低くなる
- リハビリを専門としているサービスが多い
- 利用者の体力や予定に合わせて柔軟に調整可能
- 長時間利用が難しい方や疲れやすい方にも適している
例えば、弊社リタポンテのような半日型リハビリ専門のデイサービスは、利用者の身体機能維持や改善を目指しつつ、費用面でも無理なく続けられます。
半日型デイサービスも上手に取り入れることで、補助金を利用する以外で介護費用を抑えられるでしょう。
関連記事:半日型リハビリデイサービスとは?料金・内容・メリットをわかりやすく解説
5-2.要介護度を高めないことが最大のポイント
介護費用を抑える上で最も重要なポイントは、「要介護度を高めない」ことです。要介護度が上がると、それに応じて必要となる介護サービスや医療的ケアが増え、結果として費用も大きく膨らみます。
そのため、自分の身体機能を維持・改善し、できるだけ自立した生活を続けることが経済的負担を軽減するカギと言えるでしょう。
要介護度を高めないために最も重要なことは、専門的な機能訓練に取り組むことです。
理学療法士などの支援を受けながら機能訓練に取り組むことで、日常生活において自分でできることが増え、寝たきりや重度の介護状態を防ぐことにつながります。
弊社リタポンテのようなリハビリ専門のデイサービスを利用して、要介護度を高めず、なるべく自分らしい生活を維持しましょう。
6.要介護度を高めないためにはリタポンテ型がおすすめ
要介護度を高めずに健康を維持するためには、早い段階から適切な介護予防サービスを利用することが重要です。そこで注目されるのが、介護保険制度の中でも「事業対象者認定」を受けた方が利用できる介護予防サービスです。
事業対象者認定とは、介護認定の前段階にあたり、要支援状態になるリスクがある高齢者を対象にした制度で、「介護認定を受けるより簡易な方法で、わずか2週間程度」で認定を受けられます。この認定を受けることで、まだ介護認定を受けるまでもない方でも介護予防サービスを介護保険を利用して受けられます。
リタポンテは、この事業対象者認定を活用して利用できるリハビリ専門のデイサービスです。
事業対象者認定を受けていれば、介護保険のサービス利用枠の中でリタポンテのような介護予防サービスを無理なく取り入れられるため、早期から介護リスクの軽減に取り組めます。
要介護度を高めないための第一歩として、自治体の窓口やケアマネージャーに相談し、事業対象者認定の申請を検討しましょう。ここではリタポンテの特徴や利用した人の体験談を紹介します。
6-1.リタポンテの特徴
リタポンテは、「日本から寝たきりの人をなくし、介護が必要ない未来をつくる」という強い想いのもと、ただの通所介護にとどまらない、本質的なリハビリ支援を提供しています。
日本は長寿国である一方で、高齢者の寝たきり率は世界でも最も高く、わずか数日間の入院や“寝かせきり”で歩けなくなってしまう現実があります。リタポンテは、そうした“突然の寝たきり”を防ぐために、科学的根拠に基づいたアプローチを徹底しています。
理学療法士や言語聴覚士、看護師だけでなく、足病医や痛みの専門医など、専門性の高い医師とも連携。3ヶ月ごとの体力測定や口腔機能チェックを通じて、現在の身体状態と生活課題を客観的に評価し、オーダーメイドで改善プログラムを提案しています。
私たちが目指しているのは、「できるADL(生活動作)」ではなく、「しているADL」。つまり、訓練でできるようになったことが、実際の生活で“当たり前にできている”状態をつくることです。
「歩けるようになった」だけでは終わらせません。「歩いて買い物に行けた」「自分でトイレに行けた」――その実感こそが、本当の意味での自立であり、生活の質(QOL)の向上につながります。
そして、リタポンテのリハビリは、ご家族にとっても大きな支えになります。日々の介護の中で、「つい手を出してしまう」「どう接すれば自立につながるのかわからない」と悩まれることも多いはずです。リタポンテでは、そんなご家族の戸惑いや不安にも寄り添い、一緒に“見守る力”を育てていきます。
「歳だからしかたない」とあきらめていたことが、「できるかも」に変わる瞬間。その積み重ねが、高齢者ご本人の自信となり、ご家族にとっては未来への希望になります。
リタポンテは、ご本人の「もう一度、自分の力で生きていきたい」という想いと、ご家族の「少しでも安心して見守りたい」という願いの、どちらにも応えるリハビリ専門のパートナーであり、高齢者がいつまでも「役割を持って活躍し続ける」社会を目指し、プロダクティブエイジングを推進しています。
自宅で、自分らしく暮らし続けるために。人生の可能性を信じて、もう一度チャレンジしてみませんか。
詳しくは、下記無料のLINEでもお問い合わせが可能です。
当人やご家族に役立つ介護情報なども定期的に配信していますので、まずは無料のお友達登録をしてみてはいかがでしょうか。
6-2.リタポンテを利用した人や家族の体験談
リタポンテでは、要介護2の認定を受けた方も、リハビリデイサービスを通じて、日常生活の楽しさを取り戻しています。
今回ご紹介するのは、神奈川県横浜市にお住まいの長谷川さんご家族の体験です。
コロナによる長期入院を経て退院されたお父様は、歩くこともままならず、ご家族も不安な日々を過ごしていました。そんな中、リタポンテにご相談いただき、週2回のリハビリを開始。最初はほんの数歩進むだけでも大変でしたが、スタッフが明るく寄り添いながら、一歩一歩着実にサポートしました。
リハビリに取り組むうちに、「今日は歩けた!」「疲れずに座っていられた!」と、少しずつできることが増え、ご本人もリタポンテへ通うのを楽しみにしてくださるように。半年後には、杖なしで歩行できるまでに回復され、ご家族からも「家の中が明るくなりました」とのお言葉をいただきました。
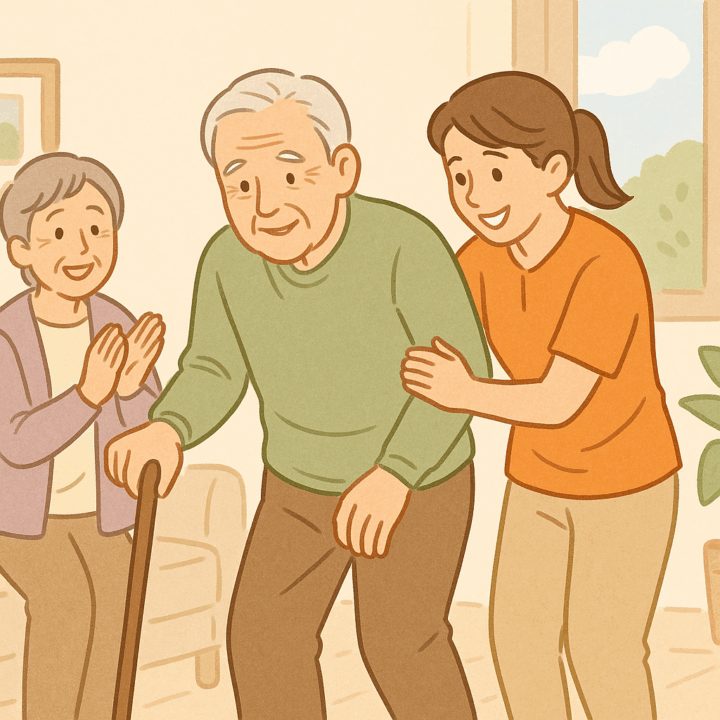
リタポンテでは、ご本人の体力や気持ちに合わせたリハビリを提供し、小さな成功体験を積み重ねることで自信と笑顔を引き出していきます。
