要介護1のデイサービスにかかる費用は?自己負担や限度額を解説
要介護1の認定を受けたご家族がデイサービスを利用する際、「実際いくらかかるの?」「負担を減らす方法はあるの?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
介護保険が適用されるとはいえ、自己負担額や施設ごとの料金体系、地域による違いなど、費用の仕組みは意外と複雑です。
本記事では、要介護1の方がデイサービスを利用した場合にかかる費用の目安や、自己負担額の具体例、施設規模・利用時間・地域による料金の違いをわかりやすく解説します。
さらに、支給限度額や費用を抑えるための軽減制度・控除制度についても丁寧に紹介しているので、初めて介護サービスを検討する方にも安心してお読みいただけます。

取締役/理学療法士上村 理絵
日本から寝たきり(寝かせきり)を無くすことを使命とする
家族がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう日常生活に必要な身体機能のリハビリに特化したディサービスを運営しています。
ご覧いただきました弊社のホームページにご案内した通り、寝たきり率が世界で最も高い日本ではリハビリを受けられない難民とも言うべき高齢者が年々増加し喫緊の社会保障制度の課題だと考えております。
そこで、この社会問題に一緒に取り組んでくれる志のあるリハトレーナーの募集を行っております。利用者・ご家族があきらめていた事を可能に変える為に…。 ぜひ、あなたからのご応募をお待ちしています!
1.要介護1のデイサービス費用は1回いくら?
要介護1の方がデイサービスを利用した場合の、1回あたりの費用について解説します。
1-1.自己負担額は1,000円~1,500円程度に収まる
要介護1の方がデイサービスを利用する際の自己負担額は、通常1回あたりおよそ1,000円〜1,500円程度に収まるのが一般的です。
介護保険が適用される基本的なサービスでは、利用者は費用の1割(一定以上の所得がある場合は2〜3割)を負担する仕組みになっています。
例えば、地域や施設によって差はありますが、7〜8時間の利用で総額が約7,000円の場合、その1割にあたる約700円が自己負担額となります。
さらに、食費やおやつ代、レクリエーション費用など、介護保険の適用外となる実費が数百円〜1,000円ほどかかります。
これらを合わせると、1回あたりの費用はおおむね1,000円〜1,500円におさまるケースが多いと言えるでしょう。
1-2.自己負担額は年金収入によって変わる
デイサービスの費用は、介護保険が適用される施設の利用料に対して、利用者が自己負担割合に応じた金額を支払う仕組みです。
自己負担割合は、利用者本人の前年の所得や同一世帯の65歳以上の数などに応じて異なり、以下のように設定されています。
- 年金収入280万円未満:1割負担
- 年金収入280万円~340万円:2割負担
- 年金収入340万円以上:3割負担
なお、本記事では要介護1の方の費用について、自己負担率1割を前提に解説を進めていきます。
1-3.デイサービスの費用が決まる5つの基準
デイサービスの費用は一律ではなく、いくつかの基準によって決まります。大きく分けて5つの要素が影響しています。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 要介護度 | 要介護1など、介護の必要度(認定区分)によって基本料金が異なる |
| 施設規模 (定員数) | 地域密着型・通常規模型・大規模型など施設規模(定員)で基本料金が変わる |
| 利用時間 | 3時間以上、5時間以上、7時間以上など、利用時間に応じて基本料金が変わる |
| 地域 | 地域区分により単価が調整される 都市部などは高め |
| サービス加算 | 入浴介助、口腔ケアなどのオプション加算がある |
これらの基準をもとに基本料金が設定され、さらに必要なサービスを追加したあとに最終的な費用が決まります。具体的な金額については、次項で詳しく説明します。
2.施設規模と時間による要介護1のデイサービス料金表
ここからは施設規模と時間による要介護1のデイサービス費用を料金表をもとに解説します。
2-1.通常規模型通所介護費の料金表
要介護1の方で通常規模型通所介護を利用する際の費用は以下のとおりです。
| 利用時間 | 要介護1の単位数 (1回あたりの自己負担額) |
|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 370円 |
| 4時間以上5時間未満 | 388円 |
| 5時間以上6時間未満 | 570円 |
| 6時間以上7時間未満 | 580円 |
| 7時間以上8時間未満 | 658円 |
| 8時間以上9時間未満 | 669円 |
通常規模型通所介護とは、ひと月あたりの利用者数が301名~750名の介護施設を指します。
2-2.大規模型通所介護費の料金表
次に大規模型通所介護費の費用を紹介します。
大規模型通所介護は以下のように利用人数によって、ⅠとⅡに分けられています。
- 大規模型通所介護(Ⅰ):ひと月あたりの利用者数が751名~900名
- 大規模型通所介護(Ⅱ):ひと月あたりの利用者数が901名以上
それぞれの介護費用は下表を参考にしてください。
【大規模型通所介護(Ⅰ)】
| 利用時間 | 要介護1の単位数 (1回あたりの自己負担額) |
|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 358円 |
| 4時間以上5時間未満 | 376円 |
| 5時間以上6時間未満 | 544円 |
| 6時間以上7時間未満 | 564円 |
| 7時間以上8時間未満 | 629円 |
| 8時間以上9時間未満 | 647円 |
【大規模型通所介護(Ⅱ)】
| 利用時間 | 要介護1の単位数 (1回あたりの自己負担額) |
|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 345円 |
| 4時間以上5時間未満 | 362円 |
| 5時間以上6時間未満 | 525円 |
| 6時間以上7時間未満 | 543円 |
| 7時間以上8時間未満 | 607円 |
| 8時間以上9時間未満 | 623円 |
通所介護費用は施設が大きくなるほど、基本報酬単価は低くなります。スタッフの数も多く、専門的な人材が配置されているケースもあります。
設備が充実している傾向もあるため、多様な介護ニーズに応えられる施設です。
2-3.地域密着型通所介護費の料金表
最後に、地域密着型通所介護の費用について紹介します。要介護1の方がこのタイプのデイサービスを利用する場合、自己負担額の目安は以下のとおりです。
| 利用時間 | 要介護1の単位数 (1回あたりの自己負担額) |
|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 416円 |
| 4時間以上5時間未満 | 436円 |
| 5時間以上6時間未満 | 657円 |
| 6時間以上7時間未満 | 678円 |
| 7時間以上8時間未満 | 753円 |
| 8時間以上9時間未満 | 783円 |
地域密着型通所介護とは、定員18名以下の小規模なデイサービスで、利用者が住み慣れた地域でサービスを受けられる点が特長です。
一人ひとりに対して手厚いケアが行えるというメリットがある一方で、費用はやや高めに設定されています。
例えば、大規模型通所介護(Ⅱ)と比べると、最大で160円ほどの差が生じることがあります。
3.デイサービス費用は地域やサービスによって加算
デイサービス費用は利用する施設の地域やオプションサービスの有無によって、基準となる単位(料金単価)が変わったり、サービス分の費用が加算されたりします。
ここでは地域やオプションサービスの有無による費用の違いを解説します。
3-1.地域差による単位換算の違い
介護報酬は通常、1単位=10円として計算されます。
ただし、地域ごとの賃金水準や物価の違いを反映するため、実際の単位あたりの金額は地域区分により若干異なることがあります。
人口や賃金水準の高い地域は1級地〜7級地に区分されており、地域区分に応じてデイサービス費の単位換算が異なるため注意が必要です。
地域区分と単位換算の違いは下表を参考にしてください。
| 地域区分 | 1単位の単価 | 該当地域の例 |
|---|---|---|
| 1級地 | 10.90円 | 東京23区 |
| 2級地 | 10.72円 | 町田市、狛江市、横浜市、川崎市、大阪市など |
| 3級地 | 10.68円 | さいたま市、千葉市、八王子市、鎌倉市、名古屋市など |
| 4級地 | 10.54円 | 牛久市、朝霞市、船橋市、立川市、神戸市など |
| 5級地 | 10.45円 | 水戸市、市川市、あきる野市、横須賀市、大津市、京都市、福岡市など |
| 6級地 | 10.27円 | 仙台市、宇都宮市、川越市、津市、明石市、和歌山市など |
| 7級地 | 10.14円 | 札幌市、新潟市、栃木市、前橋市、木更津市、豊橋市、天理市、姫路市、長崎市など |
| その他 | 10円 | 上記に該当しない地域 |
デイサービスの具体的な費用を算出する際は、厚生労働省が発表している「地域区分について」を参考にお住いの地域区分を確認しましょう。
3-2.サービス加算は施設の人員やサービス内容で変わる
デイサービスの費用は、施設の人員やサービスの内容によってサービス加算され、変動します。
ここでは人員によるサービス加算とサービス内容による加算を紹介します。
3-2-1.人員によるサービス加算
デイサービスの費用には、従業員の専門性や実務経験に応じて「サービス提供体制強化加算」が上乗せされることがあります。
サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)の区分があり、それぞれの条件に応じて加算される単位数が異なります。
| サービス提供体制強化加算の種類 | 概要 | 加算数 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 以下のいずれかに該当すること。 ①介護福祉士70%以上 ②勤続10年以上介護福祉士25%以上 | 22単位/回 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 介護福祉士50%以上 | 18単位/回 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 以下のいずれかに該当すること。 ① 介護福祉士40%以上 ② 勤続7年以上30%以上 | 6単位/回 |
介護福祉士や勤続年数の長い従業員がいるほど、サービス提供体制強化加算が追加される仕組みです。
その分費用はかかりますが、高い専門性と経験をもとに支援を実施してくれるので安心して任せられます。
3-2-2.サービス内容による加算
デイサービスは施設内で受けられるサービス内容によっても、加算されるケースがあります。下表では具体例としていくつかの加算となるサービスを掲載しているので参考にしてください。
| サービス内容 | 要件の概要 | 加算 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 入浴介助サービスを提供する際に加算される。 医師等による居宅訪問や個別入浴計画の策定・実施の有無などで「ⅠとⅡ」に分けられる。 | Ⅰ:40単位/日 Ⅱ:55単位/日 |
| 口腔機能向上加算 | 口腔機能向上を目的としたケアなどを行うサービス。 言語聴覚士や歯科衛生士など専門家の人員配置や記録・評価の有無などで、「ⅠとⅡ」に分けられる。 | Ⅰ:150単位/日 Ⅱ:160単位/日 |
| 栄養改善加算 | 栄養管理士により適切に栄養ケアを行うサービス。 | 200単位/回 |
一口にデイサービスといっても、利用できるサービスには様々なものがあります。
利用にあたって料金も変わるため、介護利用者にとってどのようなサービスが必要になるか事前に確認しておきましょう。
4.都内で要介護1のデイサービス費用シミュレーション
ここからは、都内で要介護1のサービスを利用した際にかかる費用をシミュレーションします。
回数やサービス加算の利用による違いを紹介しているので、参考にしてください。
なお、1割負担者が通常規模型通所介護施設を1回8時間以上利用したと仮定して計算しています。
4-1.要介護1でデイサービスを週3回利用した場合
都内で要介護1のデイサービスを週3回利用した場合にかかる費用を、サービス加算がない場合とある場合で紹介します。
4-1-1.サービス加算がない場合
サービス加算がない場合は、利用時間ごとの単位を地域区分に合わせて換算して、利用回数分を掛けることで算出できます。
669単位(デイサービスの利用単位)×12回(月間利用回数)×10.90(地域区分)×10%(自己負担分)≒ 8,750円(1ヶ月の介護費用)
要介護1で週3回、サービス加算無しでデイサービスを利用した場合にかかる基本の費用は、約8,750円です。
利用時間や地域によっても変動しますが、都内で1回8時間以上を週3回利用すると、上記のような金額になります。
4-2-1.サービス加算がある場合
サービス加算がある場合は、サービスによって介護費用が増加します。
例えば、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)に該当する施設で、毎回入浴介助(加算)を受けているパターンでは次のとおりです。
※今回は簡単に理解できるよう、式を分解して解説しています。
【1回あたりの単位数】
669単位(デイサービスの利用単位)+22単位(サービス提供体制強化加算)+40単位(入浴介助Ⅰ)=731単位
【週3回利用した場合の介護費用】
731単位(1回あたりの単位数)×10.90(地域区分)×10%(自己負担分)×12(月利用回数)≒ 9,561円
【週3回利用した場合の介護費用】
731単位(1回あたりの単位数)×12回(月利用回数)×10.90(地域区分)×10%(自己負担分)≒ 9,561円
サービス加算の有無によって、介護費用も大きく変わります。
4-2.要介護1でデイサービスを週5回利用した場合
次に要介護1でデイサービスを週5回利用した場合をシミュレーションします。都内で1回8時間以上の利用を仮定して計算しています。
4-2-1.サービス加算がない場合
サービス加算がない場合の計算式は以下のとおりです。
669単位(デイサービスの利用単位)×20回(月間利用回数)×10.90(地域区分)×10%(自己負担分)≒ 14,584円(1ヶ月の介護費用)
要介護1でサービス加算なしのデイサービスを週5回利用した場合にかかる費用は、約14,584円程度です。
4-2-2.サービス加算がある場合
次に前述した2つのサービス加算がある場合の週5回利用でかかる費用を見ていきましょう。
731単位(1回あたりの単位数)×20回(月利用回数)×10.90(地域区分)×10%(自己負担分)≒ 15,936円
サービス加算を利用して週5回デイサービスを利用した際は、月に1万5,000円以上かかります。
ただし、週5回デイサービスを利用するのは、現実的ではありません。要介護1におけるデイサービスの利用回数については、次の記事で詳しく解説しています。
関連記事:要介護1はデイサービスを週5回通える?回数制限や費用を紹介
5.デイサービスなど介護サービスには限度額がある
要介護1の方が利用できる介護サービスには、介護保険でカバーされる「支給限度額」が設定されています。要介護1の支給限度額は月16,765単位(167,650円)です。
支給限度額を超えない範囲内であれば、自己負担は原則1割〜3割で介護サービスを利用できます。
先ほどの週5回デイサービスに通う例(サービス加算あり)をあげると、月の単位数は14,620単位となるため限度額内に収まります。
ただし、介護サービスは訪問介護などデイサービス以外を利用するケースもあるものです。様々な介護サービスと併用することで限度額を超えてしまうこともあります。
超過分は全額自己負担となるため、事前に単位数を確認して無理のない利用計画を立てることが大切です。
6.要介護1のデイサービス費用を抑える方法は?
介護サービスの利用状況によっては、支給限度額を超えてしまうケースもあります。万が一、支給限度額を超えてしまい自己負担分が多くなってしまった場合に費用を抑える方法を解説します。
6-1.軽減制度を利用する
デイサービス費用を抑える方法として、以下の軽減制度を利用する方法が挙げられます。
6-1-1.高額介護サービス費
デイサービスをはじめとする複数の介護サービスを利用することで、月々の自己負担額が思ったより高額になった際は、「高額介護サービス費」制度が利用可能です。
高額介護サービス費制度では、1カ月あたりの自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される仕組みです。
自己負担額の上限は年収によって以下のように変わります。
| 区分 | 負担の上限月額 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 14万100円(世帯) |
| 課税所得380万円~690万円未満 | 9万3,000円(世帯) |
| 市町村民課税~課税所得380万円未満 | 4万4,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市町民税非課税 | 2万4,600円(世帯) |
| 世帯の全員が市町民税非課税かつ前年の公的年金等収入金額 + その他の所得の合計が80万円以下 | 2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 1万5,000円(個人) |
例えば、生活保護を受けている世帯の場合、上限額は月15,000円となっており、それを超えた分が後日支給されます。
制度の適用には申請が必要な場合もあるため、事前にケアマネジャーや市区町村の窓口に相談しておくと安心です。
6-2-1.高額医療・高額介護合算療養費
要介護1の方が医療費と介護費の両方で多くの自己負担が発生した場合、「高額医療・高額介護合算療養費」制度を利用することで負担を軽減できる可能性があります。
高額医療・高額介護合算療養費制度は、同一世帯内で1年間に支払った医療費と介護費の合計額が基準額を超えた場合、その超過分が払い戻される仕組みです。
具体的な基準額は下表を参考にしてください。
| 基準額 | ||
|---|---|---|
| – | 一般 | 低所得 (市町村民税非課税) |
| 現役世代 (70歳未満) | 67万円 | 34万円 |
| 後期高齢者医療費制度 | 56万円 | 31万円 |
※現役世代と同等の収入がある場合は、現役世代の基準で計算
※実際は所得や年齢に応じて6段階に基準額が設定されています。
要介護1の方でも、通院や入院、デイサービスなどを頻繁に利用していると対象となる可能性があるため、家計の負担軽減策として検討する価値があります。詳細は市区町村の窓口で確認しましょう。
6-2.控除制度を利用する
デイサービス費用を抑える方法に以下の控除制度を利用する方法もあります。
6-2-1.医療費控除
要介護1の方がデイサービスを利用する際、その費用の一部が「医療費控除」の対象となることがあります。
医療費控除は、確定申告で一定額以上の医療費を支払った場合に、所得控除を受けられる制度です。
ただし、デイサービス単体では医療費控除の対象とはならず、医師の指示に基づいて介護サービスが行われていることや、他の医療機関での治療を併用していることが必要です。
例えば、通院治療と併行して機能訓練型のデイサービスを利用している場合、その費用の一部が控除対象になることがあります。対象になるかどうかはケースバイケースなので、事前にケアマネジャーや税務署に確認しておくと安心です。
6-2-2.扶養控除
要介護1の家族を支えている方は、「扶養控除」を活用することで所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
扶養控除は、生計を一にする親族が一定の所得以下である場合、その扶養者の所得から控除を受けられる制度です。
65歳以上の要介護者を扶養している場合、「老人扶養親族」として控除額が増え、同居していれば最大58万円の控除が受けられることもあります。
特に年金収入だけで生活している高齢者の場合、扶養の対象となるケースが多く、介護費の家計負担を間接的に軽減できます。
ただし、控除を受けるためには確定申告が必要であり、要件や金額についての確認も重要です。
6-2-3.障害者控除
要介護1の方がいる場合でも、条件を満たせば「障害者控除」を受けられることがあります。障害者控除は、所得税や住民税の負担を軽減できる制度で、扶養控除などとあわせて利用することで、家計の助けになる可能性があります。
ただし注意したいのは、「要介護認定=障害者認定」ではないという点です。要介護1の認定を受けたからといって、自動的に障害者控除の対象になるわけではありません。
とはいえ、自治体によっては、要介護認定者を「障害者相当」として判断し、障害者控除の適用を認めているケースもあります。そのため、お住まいの自治体でどのような取り扱いになっているかを事前に確認しておくことが大切です。
控除が認められれば、年間で数万円の節税につながる可能性もあります。
7.要介護1でデイサービスを使うならリタポンテ型がおすすめ

リハビリ特化型デイサービスをお探しの方は、リタポンテ型のサービス利用がおすすめです。ここでは、リタポンテのサービスの特徴や体験談を紹介します。
7-1.リタポンテの特徴
リタポンテは、「日本から寝たきりの人をなくし、介護が必要ない未来をつくる」という強い想いのもと、ただの通所介護にとどまらない、本質的なリハビリ支援を提供しています。
日本は長寿国である一方で、高齢者の寝たきり率は世界でも最も高く、わずか数日間の入院や“寝かせきり”で歩けなくなってしまう現実があります。リタポンテは、そうした“突然の寝たきり”を防ぐために、科学的根拠に基づいたアプローチを徹底しています。
理学療法士や言語聴覚士、看護師だけでなく、足病医や痛みの専門医など、専門性の高い医師とも連携。3ヶ月ごとの体力測定や口腔機能チェックを通じて、現在の身体状態と生活課題を客観的に評価し、オーダーメイドで改善プログラムを提案しています。
私たちが目指しているのは、「できるADL(生活動作)」ではなく、「しているADL」。つまり、訓練でできるようになったことが、実際の生活で“当たり前にできている”状態をつくることです。
「歩けるようになった」だけでは終わらせません。「歩いて買い物に行けた」「自分でトイレに行けた」――その実感こそが、本当の意味での自立であり、生活の質(QOL)の向上につながります。
そして、リタポンテのリハビリは、ご家族にとっても大きな支えになります。日々の介護の中で、「つい手を出してしまう」「どう接すれば自立につながるのかわからない」と悩まれることも多いはずです。リタポンテでは、そんなご家族の戸惑いや不安にも寄り添い、一緒に“見守る力”を育てていきます。
「歳だからしかたない」とあきらめていたことが、「できるかも」に変わる瞬間。その積み重ねが、高齢者ご本人の自信となり、ご家族にとっては未来への希望になります。
リタポンテは、ご本人の「もう一度、自分の力で生きていきたい」という想いと、ご家族の「少しでも安心して見守りたい」という願いの、どちらにも応えるリハビリ専門のパートナーであり、高齢者がいつまでも「役割を持って活躍し続ける」社会を目指し、プロダクティブエイジングを推進しています。
自宅で、自分らしく暮らし続けるために。人生の可能性を信じて、もう一度チャレンジしてみませんか。
7-2.リタポンテを利用した人や家族の体験談
リタポンテでは、要介護1の認定を受けた方も、リハビリデイサービスを通じて、日常生活の楽しさを取り戻しています。
今回ご紹介するのは、神奈川県横浜市にお住まいの長谷川さんご家族の体験です。
コロナによる長期入院を経て退院されたお父様は、歩くこともままならず、ご家族も不安な日々を過ごしていました。そんな中、リタポンテにご相談いただき、週2回のリハビリを開始。最初はほんの数歩進むだけでも大変でしたが、スタッフが明るく寄り添いながら、一歩一歩着実にサポートしました。
リハビリに取り組むうちに、「今日は歩けた!」「疲れずに座っていられた!」と、少しずつできることが増え、ご本人もリタポンテへ通うのを楽しみにしてくださるように。半年後には、杖なしで歩行できるまでに回復され、ご家族からも「家の中が明るくなりました」とのお言葉をいただきました。
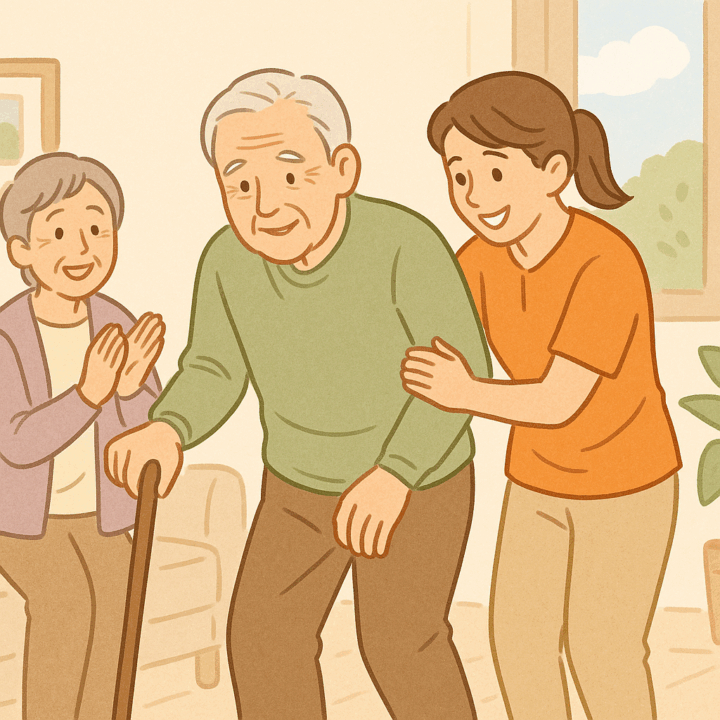
リタポンテでは、ご本人の体力や気持ちに合わせたリハビリを提供し、小さな成功体験を積み重ねることで自信と笑顔を引き出していきます。
「まだできるかも」と思える毎日を、一緒に作っていきましょう。
