デイサービスとは?簡単にわかる仕組みと目的|健康な人も通えるって本当?
「デイサービスって、そもそも何をするところ?」
「費用はどれくらいかかるの?」
親の介護や将来の備えとして気になっていても、いざ調べようとすると制度が複雑でわかりづらく、後回しにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。
デイサービスは、介護が必要な方が日中だけ施設に通い、入浴や食事、リハビリ、レクリエーションなどを受けられるサービスです。
しかし実際には、施設の種類や利用時間、要介護度によって内容や費用は大きく変わります。
本記事では、デイサービスとは何かを簡単に理解できるように、基本的な仕組みや種類、費用の目安、過ごし方までをやさしく解説します。
ご自身やご家族の将来に向けて、まずは正しく知ることから始めてみましょう。

取締役/理学療法士上村 理絵
日本から寝たきり(寝かせきり)を無くすことを使命とする
家族がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう日常生活に必要な身体機能のリハビリに特化したディサービスを運営しています。
ご覧いただきました弊社のホームページにご案内した通り、寝たきり率が世界で最も高い日本ではリハビリを受けられない難民とも言うべき高齢者が年々増加し喫緊の社会保障制度の課題だと考えております。
そこで、この社会問題に一緒に取り組んでくれる志のあるリハトレーナーの募集を行っております。利用者・ご家族があきらめていた事を可能に変える為に…。 ぜひ、あなたからのご応募をお待ちしています!
1.デイサービスとは?を簡単に解説
デイサービスとは、要介護や要支援の高齢者が日帰りで利用できる介護サービスの一つです。介護施設などに通い、日中を過ごしながら食事・入浴・機能訓練・レクリエーションなどの支援を受けられます。
ここではデイサービスの目的などを詳しく解説します。
1-1.デイサービスの目的【健康な人は使える?】
デイサービスは、基本的には要支援または要介護の認定を受けた高齢者を対象にしたサービスです。主な目的は、日常生活の支援や身体機能の維持・向上を図ることにあります。
介護を受けながらも自宅での生活を続けられるようにするためのサポートとして、多くの方に利用されています。
ただし、「要支援・要介護に該当しない=使えない」というわけではありません。実は、介護予防を目的とした「事業対象者」として認定されれば、比較的元気な高齢者でも介護保険を使ってデイサービスを利用することが可能です。
この「事業対象認定制度」は、65歳以上の高齢者が簡単なチェックリストをもとに市区町村の判定を受け、該当すれば要支援認定を待たずに利用できる仕組みです。
健康なうちから体力や生活機能を維持したい方にとって、非常に有効な制度といえるでしょう。将来の寝たきりを防ぐためにも、早めの活用がおすすめです。
1-2.デイサービスと通所介護に違いはある?
「デイサービス」と「通所介護」は、基本的には同じサービスを指します。正式な名称は「通所介護」であり、要支援・要介護の認定を受けた高齢者が、日帰りで施設に通いながら食事・入浴・リハビリなどの支援を受けられる介護保険サービスです。
一方で「デイサービス」という言葉は、一般的に使われている通称です。制度上の正式名称が「通所介護」であるのに対し、よりわかりやすく、親しみやすい言葉として「デイサービス」が広まった背景があります。
また、厳密には自治体によって「介護予防・日常生活支援総合事業」に基づいた通所型サービス(通所型サービスA・Bなど)を「デイサービス」と呼ぶこともあり、地域によって意味合いが多少異なる場合もあります。
いずれにせよ、「デイサービス」と「通所介護」は基本的に同じ仕組みと理解して問題ありません。要支援・要介護者の生活を支える在宅介護支援サービスの一環として、いずれも重要な役割を果たしています。
2.デイサービスの種類
一口にデイサービスといっても、実際には様々な種類があります。ここでは、デイサービスの種類を詳しく解説します。
2-1.施設規模の種類
デイサービスは、事業所の「月延べ利用者数」によって、以下の4つの規模に分類されます。それぞれの特徴とあわせて、メリット・デメリットを見てみましょう。
| 施設規模 | 利用者数 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 地域密着型 | 定員18名以下 | ・少人数で家庭的な雰囲気 ・スタッフとの距離が近く、柔軟な対応が可能 ・地域に根ざした運営で利用者が地元を離れる必要がない | ・プログラムの選択肢が少ない ・専門スタッフや設備が限られることも |
| 通常規模型 | 月延べ利用者数301名〜750名 | ・設備と人員のバランスが良く、平均的なサービスを受けられる ・選択肢が一定数ある | ・個別対応の柔軟さは小規模に劣る場合もある |
| 大規模型Ⅰ | 月延べ利用者数751名〜900名 | ・設備やサービスが充実しやすい ・スタッフ数が多く対応力が高い | ・利用者が多く、一人ひとりへの対応がやや機械的になることがある |
| 大規模型Ⅱ | 月延べ利用者数901名以上 | ・効率的な運営が可能で、多様なプログラムや専門職の配置も充実している | ・利用者数が非常に多く、落ち着かないと感じる方もいる ・待機時間が長くなる場合も |
このように、施設規模によって雰囲気やサービス内容に違いがあります。ご本人の性格や目的に合わせて、どの規模が適しているかを見極めることが大切です。
可能であれば、見学や体験利用を通じて、実際の雰囲気を確かめてから選ぶのが安心です。
2-2.目的別の種類
デイサービスは、法律上は一括して「通所介護」とされていますが、実際には施設ごとに特色を打ち出しており、目的別に分類されることもあります。
以下は、よく見られる目的別のデイサービスのタイプです。ただし、これらはあくまで俗称であり、制度上の正式名称ではありません。
| 種類 | 特徴・内容 |
|---|---|
| 認知症対応型デイサービス | 認知症の進行予防や緩和を目的に、専門スタッフが個別対応。 脳の活性化プログラムや少人数・家庭的な環境を重視。 |
| リハビリ特化型デイサービス | 理学療法士(PT)などの専門職が常駐または連携し、運動や機能訓練に特化。 短時間型も多く、運動プログラムが充実。 |
| 療養型デイサービス | 看護職による健康管理や医療的ケアが充実。 疾患のある方や退院直後でも安心して通えるように配慮されている。 |
このように、利用者の状態やニーズに合わせて選べるよう、多様なサービスが存在しています。目的に合ったデイサービスを選ぶことで、より満足度の高い通所介護が実現できます。
選ぶ際には、パンフレットや見学だけでなく、地域包括支援センターなどに相談して情報を集めることもおすすめです。
3.一般的なデイサービスの費用
デイサービスの費用は、介護保険制度にもとづいて計算されます。
自己負担は原則1~3割で、残りは保険から給付される仕組みです。ただし、費用の総額はさまざまな条件によって大きく変わるため、基本的な仕組みを知っておくことが大切です。
費用の基準となるのは「基本単位」と呼ばれるもので、次のような要素によって決まります。
- 要介護度(要支援1~要介護5)
- 利用する施設の規模(地域密着型(旧小規模型)・通常規模型・大規模型)
- サービスを受ける時間帯(3時間~9時間など)
例えば、要介護1の方が通常規模型のデイサービスを6時間利用した場合、584単位という基本単位が適用されます。
1単位あたりの金額は、地域ごとの物価や人件費に応じて決まる「地域区分」によって変動し、全国平均では1単位=10円ですが、東京23区などでは1単位=10.9円といったように高く設定されています。
さらに、リハビリに重点をおいた個別機能訓練、入浴介助などを受ける場合には「加算」が適用され、基本単位に上乗せされます。これらの加算内容や金額は事業所によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
最後に、利用者の収入に応じて自己負担割合(1割・2割・3割)がかかり、最終的な費用が決定されます。例えば、10,000単位のサービスを受けた場合、地域単価が10円であれば総額は10万円。このうち1割負担であれば自己負担は1万円、3割であれば3万円です。
このように、デイサービスの費用は一見わかりにくく感じるかもしれませんが、基本単位・加算・地域単価・自己負担割合の4つを理解すれば、おおよその金額が把握できます。具体的な費用を知りたい場合は、担当のケアマネージャーや利用を検討している施設に相談するのが確実です。
なお、詳しくは次の記事でも解説しているので、参考にしてください。
関連記事:要介護認定でお金はいくらかかる?もらえるお金は?自己負担・支援制度まで解説!
4.デイサービスの一般的な過ごし方
デイサービスでは、利用者が日中を安全かつ快適に過ごせるよう、さまざまなプログラムや支援が用意されています。施設によって細かな違いはありますが、一般的な一日の流れは次のとおりです。
| 時間帯 | 内容 | 概要 |
|---|---|---|
| 8:30〜9:30 | 送迎・来所 | 自宅まで送迎車が迎えに来て、職員が安全に施設まで同行する |
| 9:30〜10:00 | 健康チェック | 体温・血圧・脈拍などを測定し、当日の体調を確認 |
| 10:00〜11:30 | 入浴・機能訓練 | 希望者は入浴を行い、それ以外は個別リハビリや軽い体操を実施 |
| 11:30〜12:30 | レクリエーション | ゲーム・手作業・音楽など、楽しみながら認知機能や身体機能を刺激 |
| 12:30〜13:30 | 昼食・休憩 | 嚥下に配慮されたバランスの取れた昼食を提供し、その後は休憩時間 |
| 13:30〜14:30 | 午後の活動 | 機能訓練・趣味活動・脳トレなど、個々に合わせたプログラムを提供 |
| 14:30〜15:00 | おやつ | おやつを提供し、利用者同士の交流やリラックスタイムを楽しむ |
| 15:00〜16:00 | 帰りの準備・送迎 | 帰宅に向けた準備後、送迎車で自宅まで送り届ける |
このように、デイサービスでは日常生活に必要な支援を受けながら、身体や心の健康維持を目的としたプログラムが組まれています。
「ただ過ごす」だけでなく、楽しみや社会とのつながりを持つことができる貴重な時間として活用されています。
5.おすすめなのはリハビリ専門のデイサービス
高齢になると、少しずつ「できないこと」が増えていくのは自然なことです。しかし、「できること」を維持したり、再び「できるようになる」ためには、適切なリハビリや機能訓練を受けることがとても重要です。
一般的なデイサービスでは、入浴や食事、レクリエーションなどを通して、日常生活の維持をサポートすることが中心になります。それに対して、リハビリ専門のデイサービスでは、理学療法士(PT)などの専門職が常駐または連携し、身体機能の改善・維持に重点を置いたプログラムが提供されます。
とくにリタポンテのような施設では、要支援・要介護の認定を受けていなくても、「事業対象者認定制度」を利用することで介護保険が適用され、リハビリ専門のデイサービスを予防目的で早期に利用することが可能です。
リハビリを「必要になってから始める」のではなく、「元気なうちから始める」ことが、将来の寝たきりや要介護状態を防ぐ鍵になります。年齢にかかわらず、「今できることを続けたい」「もっと動けるようになりたい」と願う方には、リハビリ専門のデイサービスの利用が強くおすすめです。
なお、リハビリ特化型デイサービスについては、次の記事で詳しく解説します。
関連記事:リハビリ特化型デイサービスとは?料金や訓練内容など詳しく解説
6.リハビリ専門のデイサービスならリタポンテ型がおすすめ

リハビリ専門のデイサービスを利用する場合は、リタポンテのような理学療法士が常駐し、機能訓練を1時間以上行う施設を利用すべきです。
ここでは、リタポンテの特徴や利用者の体験談を紹介します。
6-1.リタポンテの特徴
「年齢を重ねると、できないことが増えるのは仕方ない」——そんな思い込みを、リタポンテはくつがえします。
私たちは、“できることを増やす”ことを本気で目指す、リハビリ専門のデイサービスです。
一般的なデイサービスでは、日中の安心な居場所を提供することに重きが置かれますが、リタポンテが目指すのは「変わる」こと。
寝たきりや要介護を防ぎ、「自分らしく生きる力」をもう一度取り戻すことに真剣に向き合っています。
そのために、私たちは以下のようなこだわりを徹底しています。
- 理学療法士による専門家主導のリハビリを実施
- 必要な機能訓練を効率よく行う短時間集中型プログラム
- 身体の状態・生活背景に合わせた完全オーダーメイド支援
- 介護認定がなくても「事業対象者」として保険利用が可能
- 現状維持でなく「できることを増やす」改善重視のリハビリ
リタポンテでは、介護予防に有効な事業対象者認定制度を活用し、まだ元気なうちから通えるリハビリの場としても多くの方に選ばれています。
年齢や体力の衰えは、放っておいても自然に戻ることはありません。
「今のうちに対策しておけばよかった」と後悔しないために、今この瞬間からの一歩が大切です。
リタポンテは、あなたのその一歩を、確かな専門性と温かい支援で全力でサポートします。
自分らしい人生をあきらめたくないあなたへ——私たちと一緒に、新しい変化を始めてみませんか?
6-2.リタポンテを利用した人や家族の体験談
リタポンテでは、リハビリデイサービスを通じて、日常生活の楽しさを取り戻しています。今回ご紹介するのは、神奈川県横浜市にお住まいの長谷川さんご家族の体験です。
コロナによる長期入院を経て退院されたお父様は、歩くこともままならず、ご家族も不安な日々を過ごしていました。そんな中、リタポンテにご相談いただき、週2回のリハビリを開始。最初はほんの数歩進むだけでも大変でしたが、スタッフが明るく寄り添いながら、一歩一歩着実にサポートしました。
リハビリに取り組むうちに、「今日は歩けた!」「疲れずに座っていられた!」と、少しずつできることが増え、ご本人もリタポンテへ通うのを楽しみにしてくださるように。半年後には、杖なしで歩行できるまでに回復され、ご家族からも「家の中が明るくなりました」とのお言葉をいただきました。
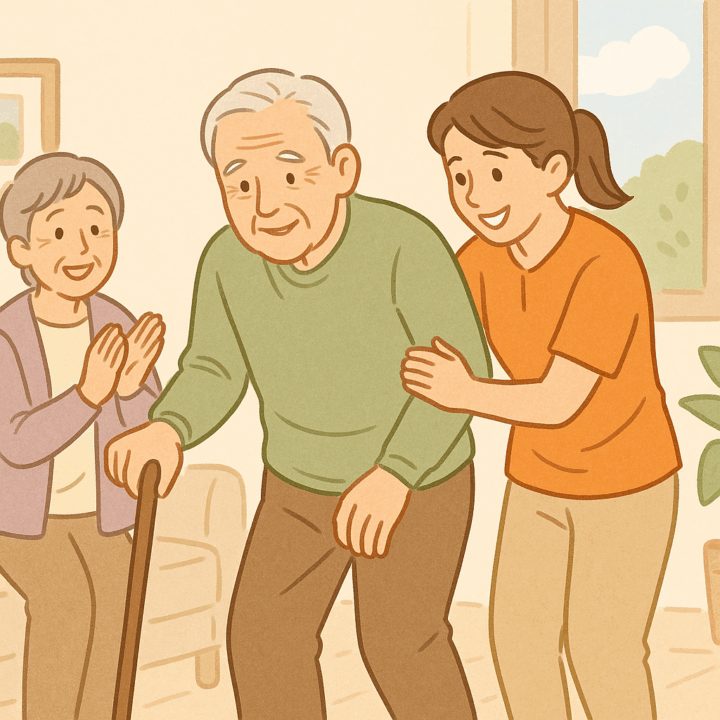
リタポンテでは、ご本人の体力や気持ちに合わせたリハビリを提供し、小さな成功体験を積み重ねることで自信と笑顔を引き出していきます。
