要介護2でデイサービスを週5回使える?何回使えるかを詳しく解説
「要介護2で週5回もデイサービスって、本当に使えるの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
結論から言えば、要介護2の方でもデイサービスを週5回利用することは可能です。
しかし、利用可能=現実的とは限らず、費用や介護保険の仕組みを知らずに使い続けると、思わぬ自己負担が発生することもあります。
この記事では、「何回使えるのか?」という素朴な疑問に明確な答えを出しつつ、支給限度額やデイサービス料金の仕組み、週5回利用した場合の具体的なシミュレーションまで、丁寧に解説します。
デイサービスだけに偏らず、訪問介護やリハビリなど要介護2で利用できる他サービスも紹介しています。
「うちの場合は?」「どこまで使えるの?」と不安を抱えるご家族にも安心して読んでいただける内容です。
本記事の情報は介護現場の実情や厚生労働省の制度に基づいた信頼性の高い内容となっているので、ぜひ最後までご覧いただき、ご自身の介護プランにお役立てください。

取締役/理学療法士上村 理絵
日本から寝たきり(寝かせきり)を無くすことを使命とする
家族がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう日常生活に必要な身体機能のリハビリに特化したディサービスを運営しています。
ご覧いただきました弊社のホームページにご案内した通り、寝たきり率が世界で最も高い日本ではリハビリを受けられない難民とも言うべき高齢者が年々増加し喫緊の社会保障制度の課題だと考えております。
そこで、この社会問題に一緒に取り組んでくれる志のあるリハトレーナーの募集を行っております。利用者・ご家族があきらめていた事を可能に変える為に…。 ぜひ、あなたからのご応募をお待ちしています!
1.要介護2でデイサービスを週5回使うことは可能
結論、要介護2でデイサービスを週5回利用することは可能です。ここでは、要介護2の方のデイサービスの利用回数について解説します。
1-1.デイサービスの利用回数に制限はない
要介護2の方がデイサービスを利用する際、法律上で「週に何回までしか使えない」といった明確な回数制限はありません。
例えば、ケアマネージャーを通じてデイサービスの利用計画を立てる場合は、本人の介護度や生活状況、家族の介護力などを踏まえて、利用回数が決定されます。
つまり、要介護2であっても、ご家族や本人、ケアマネージャーや医師などが通う必要があると判断すれば週5回利用することが可能です。
ただし、利用すればするほど、利用費も大きくなるため、介護にかけられる費用を踏まえて決定することが大切です。
1-2.毎日利用するのは現実的ではない
要介護2の方でもデイサービスを週5回利用することは制度上可能ですが、実際には「毎日利用する」というのは現実的ではないケースが多いです。
一般的には、デイサービスを週に3回から4回程度利用するのが現実的な範囲です。
これ以上の利用となると、訪問介護など他のサービスとの併用が難しくなったり、自己負担額が増えたりする可能性があります。
また、特に「リハビリ特化型デイサービス」のようにリハビリを中心とした施設の場合、利用者の身体への負担を考慮して、週2回程度の利用が一般的とされています。
無理に頻度を増やすとかえって疲労がたまり、計画的にリハビリが進められない可能性が高いです。
施設の生活相談員、理学療法士、ケアマネージャーと相談して、最適な回数を設定すると良いでしょう。
なお、リハビリ中心の施設については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:リハビリ特化型デイサービスとは?料金や訓練内容など詳しく解説
2.要介護2でデイサービスを利用する際は支給限度額に注意
要介護の方が介護サービスを利用する際に気をつけたいのが「支給限度額」です。
介護保険では、要介護度ごとに1か月あたりに使えるサービスの金額が決まっており、要介護2の場合は月額19万7,050円が上限となります。
この限度額は、デイサービスだけでなく、訪問介護や福祉用具レンタルなど、他の介護保険サービスと併用した場合も含めた合計額です。
そのため、デイサービスを頻繁に利用しながら、同時に訪問介護も利用していると、あっという間に限度額を超えてしまう可能性があります。
限度額を超えた場合、その超過分は全額自己負担となり、利用者や家族の経済的負担が大きくなってしまうため注意が必要です。
サービスを利用する際は、ケアマネージャーとよく相談し、必要なサービスを無理のない範囲で組み合わせることが大切です。
3.要介護2のデイサービスにかかる料金
ここからは要介護2のデイサービスにかかる料金を解説します。
3-1.デイサービス料金が決まる要素
デイサービスの料金は、以下の7つの要素で構成されます。
| 要素 | 解説 |
|---|---|
| 単位 | サービス費用は「単位」で計算。基本は1単位=10円。 例:370単位=3,700円。 |
| 要介護度 | 要介護度が高いほど、利用料金も高まる。 |
| 利用時間 | サービスの利用時間が長いほど、利用料金が加算される。 |
| 施設規模 | 通常規模型・大規模型・地域密着型など、施設の規模により基本単位数が異なる。 |
| 地域加算 | 地域区分によって単位単価が10円を上回ることがあり、都市部ほど高くなる傾向。 |
| オプション加算 | 入浴介助や個別機能訓練などの追加サービスは加算対象となり、単位数が増加。 |
| 自己負担割合 | 原則1割負担(一定以上所得者は2~3割)。 例:370単位なら370円~1,110円が自己負担額。 |
例えば、要介護2の方が通常規模型のデイサービスを3時間以上4時間未満利用した場合、423単位が適用され、サービス費用は4,230円となります。これに対し、自己負担が1割なら支払う金額は423円です。
また、利用する地域が都市部であれば単位あたりの金額が上がる「地域加算」がかかります。
例えば、東京23区内では1単位が10.9円と設定されているケースもあり、同じ条件での利用であっても4,610単位(461円)と高額になるのです。
入浴介助や個別リハビリなどの追加サービスを選ぶと「オプション加算」が加わり、さらに単位数が増えるため、費用が上がります。
ただし、こうした複雑な計算は利用者が覚える必要はなく、ケアマネージャーが予算や必要な支援に応じて調整してくれるため、安心して任せられます。
3-2.通常規模型を利用した場合の費用
要介護2の方がデイサービスを利用した場合の費用感を捉えるために、通常規模型事業所を利用した際にかかる単位数を時間別に紹介します。
| 利用時間 | 要介護1の単位数 (1回あたりの自己負担額の例) |
|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 423単位(423円) |
| 4時間以上5時間未満 | 444単位(444円) |
| 5時間以上6時間未満 | 673単位(673円) |
| 6時間以上7時間未満 | 689単位(689円) |
| 7時間以上8時間未満 | 777単位(777円) |
| 8時間以上9時間未満 | 791単位(791円) |
上記の金額に利用回数やオプション費用などがかけられ、最終的な介護費用が決定します。
【デイサービスの施設規模とは?】
デイサービスの施設は、ひと月あたりの利用者数に応じて以下のように分類されます。
- 通常規模型:301名~750名
- 大規模型(I):751名~900名
- 大規模型(Ⅱ):901名以上
- 地域密着型:定員18人以下
大規模型の施設は利用者数が多く、さまざまな年齢層や趣味を持つ人と交流できるため、日々の生活を楽しめる環境が整っています。スタッフも多く配置されており、多くの利用者を受け入れる体制があります。
一方、地域密着型は少人数制のため、地域に根ざしたきめ細やかなケアが可能です。利用者一人ひとりに丁寧に対応しやすいのが特徴です。
なお、施設の規模が大きくなるほど、職員が一人あたりにかけられる介護時間が相対的に短くなることから、利用料金は比較的安くなる傾向があります。
4.要介護2でデイサービスを週5回利用したシミュレーション
要介護2の方が、通常規模型のデイサービスを週5回(月20回)、8時間以上9時間未満の時間帯で利用した場合の費用シミュレーションを紹介します。
要介護2でデイサービスを8時間以上9時間未満で利用した場合の基本単位数は、791単位です。週5回利用した場合は、以下の計算になります。
791単位 × 20回 = 15,820単位(158,200円)
要介護2の支給限度額は19,705単位のため、たとえ週5回デイサービスに通ったとしても支給限度額内に収まるので、全額自己負担分は発生することはありません。
ただし、他の介護サービスとの併用やオプション加算などによっては上限を超えてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
上限額を超えないためにも、ケアマネージャーや利用するデイサービスの施設側に相談することをおすすめします。
5.要介護2の方が利用できる介護保険サービスは?
要介護2は立ち上がりや歩行などの際に介助が必要になるため、在宅生活を支えるためにさまざまなサービスを組み合わせて利用することがおすすめです。
以下に、主なサービスをカテゴリ別にまとめた表をご紹介します。
| サービス区分 | 主なサービス内容 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | ケアマネージャーによるケアプランの作成やサービス調整。 |
| 訪問系サービス | ・訪問介護(ホームヘルプ) ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回/随時対応型訪問介護 ・看護居宅療養管理指導 |
| 通所系サービス | ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) ・地域密着型通所介護 ・療養通所介護 ・認知症対応型通所介護 |
| 短期入所系サービス | ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護 |
| 複合型サービス | ・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
| 施設入所系サービス | ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設(老健) ・介護医療院 ・特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
| 福祉用具・住宅改修 | ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 ・住宅改修費の支給 |
要介護2の方は、これらのサービスを組み合わせて利用することで、在宅での生活を維持しやすくなります。
例えば、日常生活の支援として訪問介護を利用しつつ、週に数回デイサービスでリハビリや入浴支援を受けるといった組み合わせがおすすめです。
また、短期的に介護者の負担を軽減するためにショートステイを利用することもあります。
具体的なサービスの選択や組み合わせについては、ケアマネジャーと相談しながら、本人の状態や家族の状況に応じた最適なケアプランを作成することが重要です。
また、地域によって利用できるサービスや施設が異なる場合があるため、地元の介護支援専門員(ケアマネジャー)や自治体の窓口に相談することをおすすめします。
6.要介護2でデイサービスを使うならリタポンテ型がおすすめ

要介護2でデイサービスを利用する場合は、リタポンテのようなリハビリ特化型デイサービスがおすすめです。
ここでは、リタポンテのサービスの特徴や体験談を紹介します。
6-1.リタポンテの特徴
リタポンテは、「日本から寝たきりの人をなくし、介護が必要ない未来をつくる」という強い想いのもと、ただの通所介護にとどまらない、本質的なリハビリ支援を提供しています。
日本は長寿国である一方で、高齢者の寝たきり率は世界でも最も高く、わずか数日間の入院や“寝かせきり”で歩けなくなってしまう現実があります。リタポンテは、そうした“突然の寝たきり”を防ぐために、科学的根拠に基づいたアプローチを徹底しています。
理学療法士や言語聴覚士、看護師だけでなく、足病医や痛みの専門医など、専門性の高い医師とも連携。3ヶ月ごとの体力測定や口腔機能チェックを通じて、現在の身体状態と生活課題を客観的に評価し、オーダーメイドで改善プログラムを提案しています。
私たちが目指しているのは、「できるADL(生活動作)」ではなく、「しているADL」。つまり、訓練でできるようになったことが、実際の生活で“当たり前にできている”状態をつくることです。
「歩けるようになった」だけでは終わらせません。「歩いて買い物に行けた」「自分でトイレに行けた」――その実感こそが、本当の意味での自立であり、生活の質(QOL)の向上につながります。
そして、リタポンテのリハビリは、ご家族にとっても大きな支えになります。日々の介護の中で、「つい手を出してしまう」「どう接すれば自立につながるのかわからない」と悩まれることも多いはずです。リタポンテでは、そんなご家族の戸惑いや不安にも寄り添い、一緒に“見守る力”を育てていきます。
「歳だからしかたない」とあきらめていたことが、「できるかも」に変わる瞬間。その積み重ねが、高齢者ご本人の自信となり、ご家族にとっては未来への希望になります。
リタポンテは、ご本人の「もう一度、自分の力で生きていきたい」という想いと、ご家族の「少しでも安心して見守りたい」という願いの、どちらにも応えるリハビリ専門のパートナーであり、高齢者がいつまでも「役割を持って活躍し続ける」社会を目指し、プロダクティブエイジングを推進しています。
自宅で、自分らしく暮らし続けるために。人生の可能性を信じて、もう一度チャレンジしてみませんか。
6-2.リタポンテを利用した人や家族の体験談
リタポンテでは、要介護2の認定を受けた方も、リハビリデイサービスを通じて、日常生活の楽しさを取り戻しています。
今回ご紹介するのは、神奈川県横浜市にお住まいの長谷川さんご家族の体験です。
コロナによる長期入院を経て退院されたお父様は、歩くこともままならず、ご家族も不安な日々を過ごしていました。そんな中、リタポンテにご相談いただき、週2回のリハビリを開始。最初はほんの数歩進むだけでも大変でしたが、スタッフが明るく寄り添いながら、一歩一歩着実にサポートしました。
リハビリに取り組むうちに、「今日は歩けた!」「疲れずに座っていられた!」と、少しずつできることが増え、ご本人もリタポンテへ通うのを楽しみにしてくださるように。半年後には、杖なしで歩行できるまでに回復され、ご家族からも「家の中が明るくなりました」とのお言葉をいただきました。
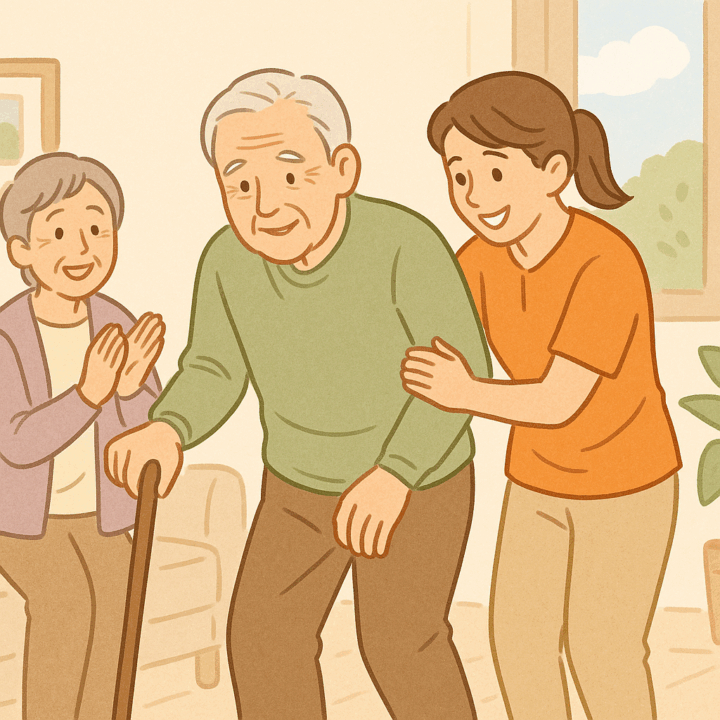
リタポンテでは、ご本人の体力や気持ちに合わせたリハビリを提供し、小さな成功体験を積み重ねることで自信と笑顔を引き出していきます。
「まだできるかも」と思える毎日を、一緒に作っていきましょう。
