要介護3でデイサービスが使える回数は?料金や自己負担を詳しく解説
要介護3でデイサービスが使える回数は?料金や自己負担を詳しく解説
「要介護3と診断されたけれど、何から始めたらいいのかわからない…」
「どれくらいデイサービスを利用できるの? 費用は? 毎日通っても大丈夫?」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?
要介護3は「寝たきり」ではないものの、自力での移動や入浴・排泄が困難になるケースが多く、家族による在宅介護には大きな負担が伴います。仕事や家庭と両立しながら介護を続けるには、適切な知識とサービスの活用が不可欠です。
この記事では、要介護3の具体的な状態やデイサービスの利用回数、料金・自己負担の目安、さらに活用できる福祉サービスの種類まで、分かりやすく丁寧に解説します。
また、リハビリを通じて機能改善を目指せる「リタポンテ」のような専門的なデイサービスの活用例もご紹介。ご本人の自立支援と、ご家族の安心を同時に叶える方法を一緒に見つけていきましょう。

取締役/理学療法士上村 理絵
日本から寝たきり(寝かせきり)を無くすことを使命とする
家族がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう日常生活に必要な身体機能のリハビリに特化したディサービスを運営しています。
ご覧いただきました弊社のホームページにご案内した通り、寝たきり率が世界で最も高い日本ではリハビリを受けられない難民とも言うべき高齢者が年々増加し喫緊の社会保障制度の課題だと考えております。
そこで、この社会問題に一緒に取り組んでくれる志のあるリハトレーナーの募集を行っております。利用者・ご家族があきらめていた事を可能に変える為に…。 ぜひ、あなたからのご応募をお待ちしています!
要介護3の状態とは?
まずは、要介護3の状態を以下の内容で解説します。
歩行が困難な状態
要介護3と認定された方は、「寝たきり」とまではいかないものの、日常生活の多くを自力でこなすのが難しい状態です。
とくに歩行に関しては、足腰の筋力が著しく低下しており、自宅内の移動すら危険を伴います。つまずきや転倒のリスクが常にあり、トイレや浴室といった生活に不可欠な場所への移動すら、大きな負担になります。
歩行器や車いすが必要となるケースもあり、ちょっとした段差や家具の配置が障害となることもあるのです。
入浴や着替え、食事などの基本動作も不安定になるため、介護者の負担は極めて大きくなります。なかには仕事を減らしたり、介護のために退職を余儀なくされたりする人もいるほどです。
介護者が自分の生活を維持しつつ、被介護者が安全な生活を送るためには、通所型や訪問型だけでなく、入居型の介護サービスの検討も必要です。
要介護2や要介護4との違い
要介護3は、介護が必要な状態の中でも中程度の位置づけであり、要介護2や要介護4とは介護の必要度や支援内容に違いがあります。
以下の表に、要介護2・3・4の主な違いをまとめました。
| 要介護度 | 主な状態の目安 | 介護者の負担 |
|---|---|---|
| 要介護2 | 一部の動作に介助が必要。 歩行や立ち上がりにふらつきがあるが、部分的には自立可能。 | 見守りや部分的な介助が中心で、負担は比較的軽い。 |
| 要介護3 | 日常生活の多くに介助が必要。歩行や立ち上がりが困難で、排泄や入浴、着替えなどに全面的な支援が必要。 物事に対する理解度の低下も見られる。 | 24時間の見守りや介助が求められ、身体的・精神的な負担が増加。 |
| 要介護4 | ほぼ全ての生活動作に介助が必要。 立ち姿勢の保持や身の回りの家事などができない。 物事に対するさらなる理解力の低下がみられる。 | 介護の手間が大幅に増え、付きっ切りの介護になるケースも。 |
要介護2では歩行や立ち上がりにふらつきが見られるだけであり、部分的な介護のみで対応できるケースが多いです。
一方、要介護3になると歩行や立ち上がりが困難になるため、日常生活の多くの場面で介助が必要です。
夜間の見守りや排せつ介助など、24時間体制での対応が求められることもあり、介助者となる家族の身体的・精神的な負担が増加します。
また、要介護4になると立ち姿勢の保持が難しくなるだけでなく、認知症の進行による理解力の低下も顕著になります。
意思疎通も難しくなるため、専門家に頼らざるを得ないケースがさらに増えるでしょう。
要介護3ではまだまだ自立的な生活ができる部分もあるため、適切なリハビリテーションや介護サービスを利用し、要介護度の進行を防ぐことが重要です。
なお、要介護2でデイサービスを利用する場合の回数や料金は、次の記事で解説しています。
関連記事:要介護2でデイサービスを週5回使える?何回使えるかを詳しく解説
要介護3でデイサービスを利用できる回数
要介護3の方であっても、デイサービスの利用回数に上限はありません。 そもそもデイサービスの利用回数に法律上の上限はなく、必要であれば毎日のように通うことも可能です。
実際、要介護3の方は歩行や排泄、入浴など、日常のあらゆる場面で手助けが必要です。
日中を自宅で過ごすとなると、介護するご家族は一日中つきっきりにならざるを得ず、身体的にも精神的にも疲弊してしまいます。
デイサービスを利用すれば、朝に送り出してから夕方まで安心して任せられるため、介護者には休息や自分の時間、仕事との両立の余裕が生まれます。
何より「自分だけで抱え込まなくていい」という気持ちのゆとりは、介護を長く続けていくうえで非常に大切です。
また、デイサービスを単なる「預かり場所」ではなく、本人の機能維持や改善を目的としたリハビリの場として活用することも可能です。
リハビリ特化型のデイサービスを活用すれば、機能改善に向けたリハビリを通じて、将来の寝たきりリスクを防ぎ、できるだけ自立した生活を目指せます。
要介護3のデイサービスにかかる料金や自己負担額は?
次に要介護3のデイサービスにかかる料金や自己負担額の目安を解説します。
利用時間と回数などによって変わる
要介護3におけるデイサービスの利用料金は、利用時間と利用回数など、以下5つの要素によって変わります。
- 利用時間
- 利用回数
- 地域加算
- オプション加算
- 自己負担割合
以下は、要介護3の方が通常規模型のデイサービスを利用した場合の、1回あたりの自己負担額の目安です(自己負担割合1割、1単位=10円で計算)。
| 利用時間帯 | 単位数 | 自己負担額(1割負担) |
|---|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 479単位 | 約479円 |
| 4時間以上5時間未満 | 502単位 | 約502円 |
| 5時間以上6時間未満 | 777単位 | 約777円 |
| 6時間以上7時間未満 | 796単位 | 約796円 |
| 7時間以上8時間未満 | 900単位 | 約900円 |
| 8時間以上9時間未満 | 915単位 | 約915円 |
ただし、要介護3の方の場合は入浴介助などのオプション加算が提供されるケースが多いため、表中の自己負担額より高額になることが見込まれます。
また、昼食代やおやつ代、オムツ代などは介護保険の適用外となり、実費負担となります。
デイサービスの施設規模とは?
デイサービスの施設は、ひと月あたりの利用者数に応じて以下のように分類されます。
- 通常規模型:301名~750名
- 大規模型(I):751名~900名
- 大規模型(Ⅱ):901名以上
- 地域密着型:定員18人以下
大規模型の施設では利用者が多く、幅広い世代や多様な趣味を持つ人々と交流する機会が豊富にあります。そのため、刺激のある生活を送りやすく、楽しみを感じやすい環境が整っています。また、スタッフの人数も充実しており、多人数の受け入れにも対応可能です。
対して、地域密着型の施設は定員が少ない分、地域性を活かしたサービスや個別対応に力を入れやすい点が魅力です。少人数ならではの距離感で、利用者一人ひとりに寄り添った丁寧な介護が行われます。
なお、一般的に規模が大きくなるほど、職員が対応する利用者数が増えるため、1人あたりの介護時間は短くなる傾向があります。その分、費用面では比較的リーズナブルな料金設定となるケースが多いです。
支給限度額を超えると全額自己負担になる
介護保険制度には、要介護度ごとに月あたりの支給限度額が定められており、要介護3では27,048単位(約270,480円相当)が上限です。
この範囲を超えてサービスを利用すると、超過分は介護保険の対象外となり、全額自己負担になります。
実際に「それほど使わないから限度額を超えることはない」と思われがちですが、現実には限度額を超えてしまうケースも少なくありません。
生命保険文化センターが2025年1月に発表した「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によれば、介護にかかる自己負担費用(月額)は平均8万9,500円という結果が出ています。
これはデイサービスだけでなく、訪問介護・福祉用具・医療費なども含めた実費ですが、介護度が高く、サービス利用が頻繁な方ほど限度額を超えるリスクは高まる傾向にあります。
このような金銭的負担を抑えるには、ケアマネジャーと密に連携し、サービス利用状況や回数を定期的に見直すことが非常に重要です。
限度額を超えないよう配慮しながら、必要な支援をバランスよく受ける体制づくりが求められます。
要介護3に合った福祉サービスを選ぶことが大切
要介護3は立ち上がりが困難になるなど運動機能の低下が見られるだけでなく、認知症の進行などによってコミュニケーションを取るのが難しくなるケースも見られます。
そのため、介護者の実態に合った福祉サービスを上手に併用することがおすすめです。ここでは、要介護3の方が利用できる福祉サービスやおすすめサービスを紹介します。
要介護3で利用できる福祉サービス一覧
要介護3の方は、介護保険制度に基づき、以下のような多様な福祉サービスを利用できます。
これらのサービスは、在宅での生活支援から施設入所まで幅広く対応しており、個々の状況やニーズに応じて選択・組み合わせることが可能です。
| サービス区分 | サービス名 | 概要 |
|---|---|---|
| 訪問型サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う。 |
| 訪問入浴介護 | 専用の入浴設備を持ち込み、自宅での入浴介助を提供。 | |
| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、医療的なケアや健康管理を行う。 | |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士等が自宅を訪問し、リハビリを実施。 | |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間や早朝に訪問し、必要な介護を提供。 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間体制で定期的な巡回や随時の対応を実施。(夜間対応型訪問介護と統合予定) | |
| 通所型サービス | 通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、食事や入浴、機能訓練などを受ける。 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や病院が併設された施設に日帰りで通い、主治医の指示の元、リハビリを中心としたサービスを受ける。 | |
| 地域密着型通所介護 | 小規模な施設で、地域に密着した通所介護を提供。 | |
| 療養通所介護 | 難病や末期がんなど医療的ケアが必要な方を対象にした通所サービス。 | |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象にした専門的な通所介護を提供。 | |
| 短期入所サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 自宅での自立した生活を目標に短期間施設に入所する。 |
| 短期入所療養介護 | 自立した生活を目標にリハビリ等の医療的ケアを行いながら短期入所するサービス。 | |
| 複合型サービス | 小規模多機能型居宅介護 | 通いを中心に、訪問や宿泊を組み合わせたサービスを提供。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービス。「通い」「泊り」「訪問看護」「訪問介護」のサービスを提供。 | |
| 施設入所サービス | 特別養護老人ホーム(特養) | 常時介護が必要な方が長期入所し、生活全般の支援を受ける。 |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指す方がリハビリを中心に短期入所する。 | |
| 介護医療院 | 医療と介護を一体的に提供する長期療養型の施設。 | |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) | 有料老人ホーム等で、介護サービスを受けながら生活できる施設。特養とは入居条件や施設形態が異なる。 | |
| 福祉用具・住宅改修 | 福祉用具貸与 | 車いすや介護ベッドなどの福祉用具をレンタル。 |
| 特定福祉用具販売 | 入浴補助用具やポータブルトイレなどの購入。 | |
| 住宅改修費支給 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修に対する費用を支給。 | |
| 相談支援サービス | 居宅介護支援(ケアマネージャー) | ケアプランの作成やサービス提供事業者との連絡・調整。 |
数ある福祉サービスの中で、どのサービスを利用すべきかは、介護者本人や家族の意思などによって異なります。
ケアマネージャーと相談しながら、本人と家族にとって最善のケアプランを考えましょう。
要介護3はリハビリ特化型デイサービスを利用しよう
要介護3の方は、歩行や立ち上がりが困難となり、日常の動作が難しいケースが多いです。しかし、適切なリハビリを受けることで、できることが少しずつ増えていく可能性があります。
リハビリと聞くと「筋トレのようなきつい運動」をイメージするかもしれませんが、実際はもっと生活に密着した機能訓練です。
例えば「自分で立ち上がる」「トイレに行く」「着替えをする」など、本人の「できる」を引き出すことを目的としています。
特に弊社リハビリ専門のデイサービス「リタポンテ」では、一般的なデイサービスでは受けられない、以下のような専門的なサポートを行っています。
- 医師や理学療法士と連携した個別リハビリの実施
- ひとりひとりに合せたオーダーメイドプログラムの策定
- 3ヵ月ごとの体力測定と口腔機能チェック
- 生活上の課題を本人や家族と共有し改善
- 寝たきりにさせない厳選したトレーニング機器の使用
弊社リタポンテのようなリハビリ専門のデイサービスを活用すれば、介護者の負担を減らしつつ、介護者本人の機能改善や、それに伴う認知機能の改善を目指すことが可能です。
なお、リハビリ専門のデイサービスについては、次の記事で解説しています。
関連記事:リハビリ特化型デイサービスとは?料金や訓練内容など詳しく解説
要介護3でデイサービスを使うならリタポンテ型がおすすめ
要介護3でデイサービスを利用する場合は、リタポンテのようなリハビリを専門とするサービスの利用がおすすめです。
ここでは、リタポンテの特徴や利用者の体験談を紹介します。
リタポンテの特徴
リタポンテは、「日本から寝たきりの人をなくし、介護が必要ない未来をつくる」という強い想いのもと、ただの通所介護にとどまらない、本質的なリハビリ支援を提供しています。
日本は長寿国である一方で、高齢者の寝たきり率は世界でも最も高く、わずか数日間の入院や“寝かせきり”で歩けなくなってしまう現実があります。リタポンテは、そうした“突然の寝たきり”を防ぐために、科学的根拠に基づいたアプローチを徹底しています。
理学療法士や言語聴覚士、看護師だけでなく、足病医や痛みの専門医など、専門性の高い医師とも連携。3ヶ月ごとの体力測定や口腔機能チェックを通じて、現在の身体状態と生活課題を客観的に評価し、オーダーメイドで改善プログラムを提案しています。
私たちが目指しているのは、「できるADL(生活動作)」ではなく、「しているADL」。つまり、訓練でできるようになったことが、実際の生活で“当たり前にできている”状態をつくることです。
「歩けるようになった」だけでは終わらせません。「歩いて買い物に行けた」「自分でトイレに行けた」――その実感こそが、本当の意味での自立であり、生活の質(QOL)の向上につながります。
そして、リタポンテのリハビリは、ご家族にとっても大きな支えになります。日々の介護の中で、「つい手を出してしまう」「どう接すれば自立につながるのかわからない」と悩まれることも多いはずです。リタポンテでは、そんなご家族の戸惑いや不安にも寄り添い、一緒に“見守る力”を育てていきます。
「歳だからしかたない」とあきらめていたことが、「できるかも」に変わる瞬間。その積み重ねが、高齢者ご本人の自信となり、ご家族にとっては未来への希望になります。
リタポンテは、ご本人の「もう一度、自分の力で生きていきたい」という想いと、ご家族の「少しでも安心して見守りたい」という願いの、どちらにも応えるリハビリ専門のパートナーであり、高齢者がいつまでも「役割を持って活躍し続ける」社会を目指し、プロダクティブエイジングを推進しています。
自宅で、自分らしく暮らし続けるために。人生の可能性を信じて、もう一度チャレンジしてみませんか。
リタポンテを利用した人や家族の体験談
リタポンテでは、要介護2の認定を受けた方も、リハビリデイサービスを通じて、日常生活の楽しさを取り戻しています。
今回ご紹介するのは、神奈川県横浜市にお住まいの長谷川さんご家族の体験です。
コロナによる長期入院を経て退院されたお父様は、歩くこともままならず、ご家族も不安な日々を過ごしていました。そんな中、リタポンテにご相談いただき、週2回のリハビリを開始。最初はほんの数歩進むだけでも大変でしたが、スタッフが明るく寄り添いながら、一歩一歩着実にサポートしました。
リハビリに取り組むうちに、「今日は歩けた!」「疲れずに座っていられた!」と、少しずつできることが増え、ご本人もリタポンテへ通うのを楽しみにしてくださるように。半年後には、杖なしで歩行できるまでに回復され、ご家族からも「家の中が明るくなりました」とのお言葉をいただきました。
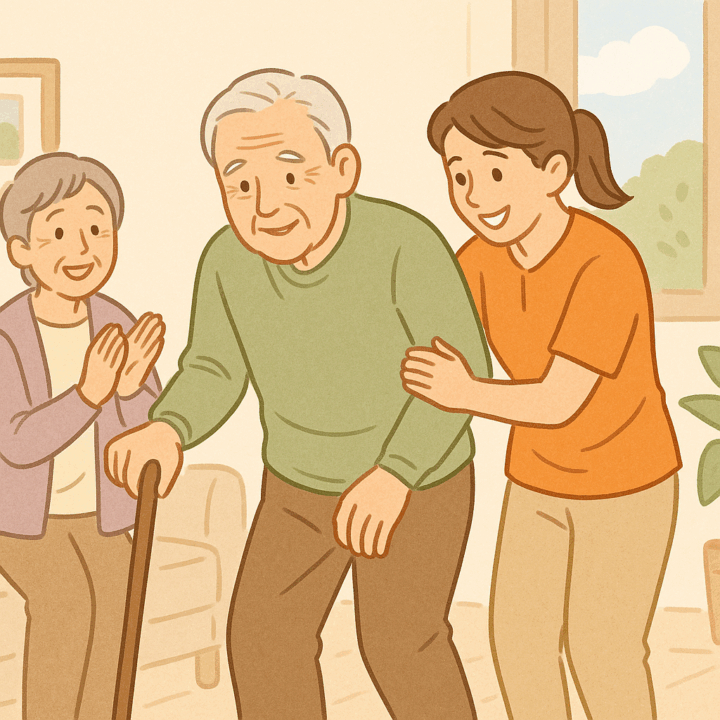
リタポンテでは、ご本人の体力や気持ちに合わせたリハビリを提供し、小さな成功体験を積み重ねることで自信と笑顔を引き出していきます。
「まだできるかも」と思える毎日を、一緒に作っていきましょう。
要介護3に関するよくある質問
最後に要介護3に関するよくある質問に回答します。
要介護3は在宅介護は無理?
要介護3の方の在宅介護は「無理」ではありませんが、現実には多くの課題があります。
介護者の負担が大きく、特に夜間の排泄介助などが睡眠不足やストレスの原因となり、生活に大きな影響を及ぼします。
そのため、在宅介護を行う場合は、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの介護保険サービスを組み合わせることになるでしょう。
例えば、平日は訪問介護や通所介護を利用しつつ、休日は介護者の負担を減らすために短期入所生活介護などを利用する方法があります。
リハビリ特化型のデイサービスも併用することで、機能改善を行いながら在宅介護を継続することも目指せます。
要介護3でもらえるお金はある?
以下に、要介護3でもらえる・利用できるお金や経済的支援制度を表にまとめました。ご家族が情報を整理しやすいよう、制度の種類・内容・主な条件を明確に記載しています。
| 制度名 | 内容 | 対象・条件 |
|---|---|---|
| 高額介護サービス費制度 | 所得に応じた月額上限を超えた介護費が払い戻される | 上限例:住民税非課税世帯で15,000円など |
| 障害者控除 | 障害者認定を受けた場合は所得税・住民税の控除対象になる | 納税者本人や同一生計になる家族が障害を持っている場合 |
| おむつ代助成制度 | おむつ購入費用の一部を給付または現物支給 | 市町村ごとに異なる 要介護3以上でおむつ使用がある人が対象 |
これらの制度をうまく活用することで、介護にかかる経済的な負担を減らせます。
ご家族の状況に合った制度を選ぶためにも、ケアマネジャーや市町村の福祉課に相談することをおすすめします。
要介護3から回復することはない?
要介護3の状態からの回復は可能です。適切なリハビリテーションや介護サービスの利用により、要介護度が改善するケースが報告されています。
事実、弊社リタポンテのご利用者様の中には、要介護5の状態からリハビリを続け、1人でトイレやリビングに移動できるようになった方もいらっしゃいます。
要介護3は不安定でありながらも、自立や歩行ができるケースも多いため、リハビリによって機能改善や寝たきり予防に努めることは十分可能です。
正しいリハビリは機能改善だけでなく、認知症予防やメンタルケアにも効果的であるため、要介護認定を受けたからと諦めず、前向きに取り組むことが大切です。
